禊は、神事に先立つ潔斎としても実践され、民俗学者の折口信夫は禊について「神事に当る為の用意として、予め、心身を清めておくことである。家でも身体でも、神に接する為の資格を得る方法である。吉事をまつため、迎ふる為の行事は、禊である」と述べています。
禊の神話的起源は、伊邪那岐命(イザナギノミコト)が死者の国である黄泉国から帰ってきたときに、死者の国の穢れを祓うために筑紫日向橘小戸の阿波岐原で禊祓を行ったことにあるとされています。天照大神、須佐之男命、月読命の三柱の神様は、この禊により生まれた神様です。
 禊の作法や次第にもいくつかの形があるようですが、現在神社本庁が採用している禊の行法(神社本庁研修所禊祓行事次第参照)は、明治から昭和初期にかけて活躍した神道家・川面凡児(かわつらぼんじ)によって復興・整備されたものが元になっております。昭和になってから、川面凡児のその行法を大政翼賛会が国民運動として取り入れ、それがさらに改編されて、現在の形になりました。この行法では、水を被る、もしくは浸かる前に、参加者たちは鳥船(とりふね)行事、雄健(をたけび)行事、雄詰(をころび)行事、気吹(いぶき)行事といわれる所作を行うことになっており、禊は必ず、これらの行事とセットで行われます。 禊の作法や次第にもいくつかの形があるようですが、現在神社本庁が採用している禊の行法(神社本庁研修所禊祓行事次第参照)は、明治から昭和初期にかけて活躍した神道家・川面凡児(かわつらぼんじ)によって復興・整備されたものが元になっております。昭和になってから、川面凡児のその行法を大政翼賛会が国民運動として取り入れ、それがさらに改編されて、現在の形になりました。この行法では、水を被る、もしくは浸かる前に、参加者たちは鳥船(とりふね)行事、雄健(をたけび)行事、雄詰(をころび)行事、気吹(いぶき)行事といわれる所作を行うことになっており、禊は必ず、これらの行事とセットで行われます。
鳥船(とりふね)行事というのは、道彦(みちひこ)と呼ばれる代表先導者と、その道彦の補助である助彦(すけひこ)の先導により、大発声をしながら船を漕ぐ所作をすることで、定められた作法と言霊と呼吸法により心身と霊魂を浄化統一する所作であり、冷水に浸かる前の準備運動としての性格も併せ持っています。
そして鳥船行事を行った後は、雄健(おたけび)行事、雄詰(おころび)行事、気吹(いぶき)行事という所作を順番に行います。雄健とは、神我一体の真我となる秘法、雄詰とは、神威を如実に顕すところの「神叫び」、気吹とは、日本民族独特の「神の呼吸法」です。
これら一連の所作(鳥船、雄健、雄詰、気吹)を終えてから、実際に水で身体を濯ぎ清めるわけですが、この濯ぎ清めるという所作もその場・状況に合わせて様々な形があり、一般的には、井戸・水槽・容器などの中に貯まった水を桶ですくって肩から被る、もしくは、海・河川・湖・池などに入り肩もしくは胸まで水に浸かる、あるいは、滝に入り頭もしくは肩から水に打たれる、とった形で執り行われます。
 明治時代の海軍軍医で、慈恵医大の創始者である高木兼寛によると、禊には、罪穢れや災厄が祓われるという本来の宗教的効果とは別に、次に挙げる3点の肉体的な効用があるそうです。 明治時代の海軍軍医で、慈恵医大の創始者である高木兼寛によると、禊には、罪穢れや災厄が祓われるという本来の宗教的効果とは別に、次に挙げる3点の肉体的な効用があるそうです。
- 寒さに対抗して赤血球が増え酸素(熱量)が増大し寒さに強くなる。
- 体表血管が拡張し血流が盛んになり活性化する。
- 血液の濃度に変化がみられるようになり内臓諸器官に抵抗力がつく。
また、禊の精神的効用としては、次の4点を挙げています。
- 間違った生活から救われ、難病が癒えて、健康長寿となる。
- 妄見を脱することができる。
- 三世一貫、顕幽一体の安心立命に立つことがきる。
- 祖先や先人を浄化し、神化し、永遠の生命に生きるようになる。
このように、禊は実践することにより、肉体的・精神的に様々な効果が得られます。ただし、既に述べましたように禊には定められた作法や所作があり、ただ闇雲に水を被ればいい、というものではありません。神道であろうと仏教であろうと、あるいは修験道であろうと、宗教における行法を実践するに当たって最も重要なのは心構えであり、作法などの“形”は、行法本来の意味からいえば副次的なものといえますが、しかし形式が人間の精神生活を規定する力を持っていることも無視できない事実であり、それ故、宗教における行法は、幾多の変遷を経ながらも先人たちにより定められた形式を踏襲し、実践することに、大きな意味があるのです。
勿論、形を重視するあまり、精神が疎かになってしまっては、それこそ本末転倒です。信なき禊はただの水浴びに過ぎず、禊は、身体の禊であるとともに心の禊であることも忘れてはいけません。
禊祓行事次第
 當日早旦禊祓場を辨備す 當日早旦禊祓場を辨備す- 其の儀禊祓場の周辺に齋竹を立て、注連縄を張り渡す。
- 時刻道彦及び受講者参進 是より先手水の儀あり
- 其の儀受講者代表紳籬を捧持し、道彦の先導に依り、列次を整へて進む。
- 次に道彦及び受講者禊祓場に著く
-
- 次に脱衣
-
- 次に参加者各其の位置に整列す
- 其の儀道彦の指示に依る。
- 次に受講者代表神籬を禊祓場中央奥に建つ
-
- 次に祓詞を齊唱す
- 其の儀紳籬に向ひ、道彦の先導に依り、先づ再拝、次に祓詞を齊噌し、畢りて再拝二拍手一拝す。
- 次に烏船行事
- 其の儀第一段は、先づ左足を斜左前に踏み出すと同時に両手を突出して握り、上体を前に倒してから両手を引寄せ、次に前下方へ突出す。引寄する時に「イーエッ」、突出す時に「工ーイッ」と唱へ、之を繰返す。次に道彦の合図に依り元の姿勢に復し、瞑目して「祓戸大神」と連唱しつつ振魂(振魂は両手を臍下前方に右手を上にして掌を軽く組合はせ、連続して上下に振り動かす)を行ふ。
第二段は、右足斜め右前に踏み出し、両手を引き寄する時に「工ーイッ」、突出す時に「ホ」と唱へる外は第一段に同じ。
第三段は、左足を左斜前に踏み出し、両手を引寄する時に「工ーイッ」、突出す時に両手を開いて「サ」と唱へる外は第一段に同じ。
- 次に雄健行事
- 其の儀足を開き、両手を腰に當て、道彦の綾聲に從ひ
「生魂・足魂・玉留魂」
と唱ふ。
- 次に雄詰行事
- 其の儀、左足を斜前に踏み出し、左手は腰に當て、右手は第一・第四・第五指を折り、第二・第三指を立てて眉問の邊に構へ、「国常立命」と叫ぶ。次に「イーエッ」の氣合と共に右手にて空問を斜左方に切り下ろすと同時に右足を左足にそろへる。次いで「エーイッ」の氣合と共に右手、右足を元に戻す。(三度反復)
-
 次に気吹行事 次に気吹行事
- 其の儀両手を拡げて差上げると同時に大気を静かに腹中に収め、次に両手を頭上にて組み、徐々に下げながら上体を屈するに從ひ、静かに息を吐く。(三度反復)
- 次に身滌行事
- 其の儀「工ーイッ」の氣合と共に水に入る。次いで振魂しつつ大祓詞を齊唱す。振魂の間「祓戸大神」を連唱す。
- 次に鳥船行事
- 其の儀前に同じ。
- 水に雄健行事
- 其の儀前に同じ。
- 次に雄詰行事
- 其の儀前に同じ.
- 次に氣吹行事
- 其の儀前に同じ.
- 次に著衣
-
- 次に各退下
- 其の儀受講者代表神籬を捧持し、道彦の先導に依り列次を整へて退く。
附 記
- 服装は白衣・白跨・鉢巻・素足・白緒草履とす。
- 豫め脱衣のまま参進の場合は、脱衣の項を省く。
- 身滌の際、男子は白鉢巻・白褌、女子は白鉢巻・白半長襦袢・白帯・白下ばき等を着用するものとす。
- 烏船行事の問、適宜鳥船行事の和歌を唱ふ。
鳥柵行事の和歌
朝タに 神の御前に みそぎして すめらが御代に 仕へまつらむ
イーエツ。工ーイツ。
遠つ神 固め修めし 大八洲 天地共に とはに榮えむ。
エーイッ。ホ。
天津神 國津神たち みそなはせ おもひたけびて 我が為す業を
エーイ。サ。
参加者募集
- 【実施日時】
- 随時募集。
当日の午前8時までに西野神社社務所に集合して下さい。
- 【参加資格】
- 誰でも参加できます。ただし、冷水を被るため、心臓の弱い方の参加は御遠慮下さい。
- 【参加申込】
- 西野神社社務所まで電話でお申し込み下さい。
(011-661-8880)
- 【参加費】
- 無料
- 【御用意していただくもの】
- 濡れた体を拭くバスタオルは各自で御用意下さい。
- 鉢巻やフンドシは当社で用意させていただきます。
- 事前に白衣を用意する都合上、女性の参加希望者はなるべくお早めにお申し込み下さい。
- 当日、悪天候でも禊は決行いたします。
- 禊終了後、参加者には記念品をお渡し致します。
- 体調等の都合から当日水を被ることができない方については、参加せずに、見学するだけでも構いません。
- 御不明な点は、西野神社社務所までお問い合わせ下さい。
|
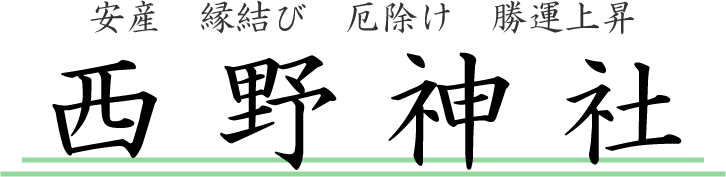
 禊の作法や次第にもいくつかの形があるようですが、現在神社本庁が採用している禊の行法(神社本庁研修所禊祓行事次第参照)は、明治から昭和初期にかけて活躍した神道家・川面凡児(かわつらぼんじ)によって復興・整備されたものが元になっております。昭和になってから、川面凡児のその行法を大政翼賛会が国民運動として取り入れ、それがさらに改編されて、現在の形になりました。この行法では、水を被る、もしくは浸かる前に、参加者たちは鳥船(とりふね)行事、雄健(をたけび)行事、雄詰(をころび)行事、気吹(いぶき)行事といわれる所作を行うことになっており、禊は必ず、これらの行事とセットで行われます。
禊の作法や次第にもいくつかの形があるようですが、現在神社本庁が採用している禊の行法(神社本庁研修所禊祓行事次第参照)は、明治から昭和初期にかけて活躍した神道家・川面凡児(かわつらぼんじ)によって復興・整備されたものが元になっております。昭和になってから、川面凡児のその行法を大政翼賛会が国民運動として取り入れ、それがさらに改編されて、現在の形になりました。この行法では、水を被る、もしくは浸かる前に、参加者たちは鳥船(とりふね)行事、雄健(をたけび)行事、雄詰(をころび)行事、気吹(いぶき)行事といわれる所作を行うことになっており、禊は必ず、これらの行事とセットで行われます。 明治時代の海軍軍医で、慈恵医大の創始者である高木兼寛によると、禊には、罪穢れや災厄が祓われるという本来の宗教的効果とは別に、次に挙げる3点の肉体的な効用があるそうです。
明治時代の海軍軍医で、慈恵医大の創始者である高木兼寛によると、禊には、罪穢れや災厄が祓われるという本来の宗教的効果とは別に、次に挙げる3点の肉体的な効用があるそうです。 當日早旦禊祓場を辨備す
當日早旦禊祓場を辨備す 次に気吹行事
次に気吹行事