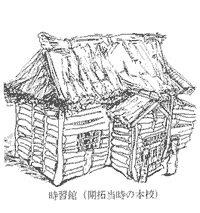 |
| 時習館(開拓当時) |
明治11年(1878年)開拓使庁から官費100円と村の人たちの寄付金70円を合わせて、土地を約900平方メートル建物約50平方メートルの校舎を新ちくして、時習館を上手稲教育所(宮の沢1北2)と名前をかえました。
明治13年(1880年)には公立上手稲小学校となり必ず学校へ行かなければ行けない年数が3年になりました。
 |
| 明治42年にできた校舎 |
このころの道は原野の中のふみつけた道で、森の中は左右にまがりくねって、沢があったり、しっちだったり、くまの通り道だったり子どもがひとりで学校に行くのはたいへんでした。明治24年(1889年)分教場ができました。
明治28年(1895年)には公立上手稲尋常小学校となり4年間必ず学校へいくようになり、明治41年には今と同じように6年間学校に通うようになりました。
でも、明治10年(1877年)ころは江戸時代の考え方がのこっていて、男の子は字をおぼえなければいけないが、女の子は、「学校に行くとなまいきになる。子守でもさせておけばいい」というような考えで
、学校に行かなければいけない子供のうち60%しか学校に行っていませんでした。そのうち、女子は3分の1だったそうです。(札幌市街では明治40年に99%の子供が学校に行っていました)
さらに学校にも、天皇へい下・皇后へい下の写真や教育勅語がくばられ、忠君愛国の精神教育にはげむことになり修身が重要な科目になりました。教科書は明治37年(1904年)国定教科書になり、全国どこの小学校も同じ教科書をつかうようになり、教育のしくみを強めてきました。
大正時代 大正6年(1917年)4月1日に高等科ができ上手稲尋常高等小学校と名前をかえました。大正6年の進学率は43%で今のように全員が中学校に進学しませんでした。昭和8年ごろには、男子だけ90%の進学率になりましたが、女子は50%になっただけでやはり家事手伝いという家庭が多かったようです。
出席率も、農家の家庭が多かったので、手伝いで休みが多く、あまりよくありませんでした。そのため、休みすぎで進級できない子もたくさんいました。
教科書は全国同じものをつかっていました。教科は修身、国語(読み方、綴りかた、書き方)算術(算数、珠算)国史、地理、理科、図画、唱歌、たいそう、さいほうがありました。理科は4年生から、国史、地理は5年生から、さいほうは4年生以上の女子だけがならいました。中でも修身の教科はとくに力をいれて教育され、教育勅語や戊申詔書(1908年(明治41年)、明治天皇のおことば。国民の教育基本として日露戦争の勝利でうわついた心をいましめ、けんじつな生活をとうとぶよう、といたものです)をいっしょうけんめいに、あんしょうしました。さいほうは、女の子が自分の着る物は自分でぬえるようにとさいほう講習を毎年おこない、どりょくしていました。
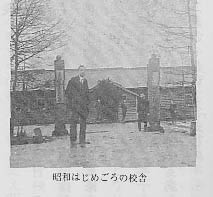 |
| 昭和はじめごろの校舎 |
昭和時代 昭和6年ごろから天候ふじゅん、世界的けいざいふきょう、満州事変のえいきょうで、世の中がみだれ食べ物にこまる人がおおくなりました。さいわい西野地域は、農村地帯のため欠食児童、栄養不良児童はあまりいませんでしたが、学用品の不足や必需品や通学のための必要品(ゴムぐつなど)が不足しましたが、不足児童には、学用品、教科書は与えられました。
 |
| 昭和9年にできた校舎 |
太平洋戦争のころ 昭和6年(1931年)の満州事変から、日本は対外的に多くの問題にぶつかり、教育にもしだいにえいきょうしてきました。昭和12年(1937年)の日華事変以後、きゅうに戦争のえいきょうを受け、国のためにという教育が行われるようになり、小学校も国民学校と名前が変わりました。男は剣道・柔道、女はなぎなたが教えられ、ならびかた、行進の練習をいつもしました。
昭和16年(1941年)太平洋戦争が始まり、男は兵士として出征していき、労働力が不足していきました。そのため、田植えや稲刈り時期には、農繁休業といって学校を休み子供たちは農家の仕事に協力しました。
戦争も終わりに近づくと高等科の生徒は農家や工場にてつだいに行きべんきょうは、ほとんどできなくなりました。
戦後 第二次世界大戦は昭和20年(1945年)8月15日に終わりましたが、国民の多くは精神的に混乱ました。古い伝統にささえられた、いままでの日本の教育は新しい教育のしくみを作ることがひつようになりました。
戦時中の「国のため」という考えや戦争のえいきょうを受けた教育のしかたをやめて、文化的で平和な国づくりを目的とした民主教育が進められました。戦時中つかわれた教科書の、戦争のことが書かれた部分や神社、軍人のことを書いたところは、墨で塗りつぶしてつかいました。
 |
| 昭和53年にできた現校舎 |
昭和22年(1947年)11月3日、日本の憲法が新しく作られ、「ぜったいに戦争をしない」「人間はみな平等でしあわせになる権利がある」「政治は国民が行う」という民主主義のもとができました。それをもとに「教育基本法」「学校教育法」という教育のもとになる考えができ昭和22年4月から6・3・3・4という新しい教育の仕組みができあがりました。義務教育の年数も、小学校が6年、中学校が3年の合わせて9年となりました。
昭和22年(1951年)手稲中学校上手稲分校(3学級)が併置され昭和27年(1952年)手稲町立上手稲中学校、手稲町立手稲東小学校と名前を変え昭和37年(1962年)現在の地に移転しました。昭和42年(1976年)札幌市立手稲東小学校となる。
教育目標
| 1、 |
明るい子 |
美にあこがれおもいやりあふれる明るい子ども |
| 2、 |
考える子 |
進んで学び相違を生かして考える子ども |
| 3、 |
ねばり強い子 |
健康で気力に満ちたねばり強い子ども |
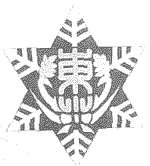 |
| 手稲東小校章 |
校章のこころ
中央に、校名にある「東」と「小」、たくさんとれた手稲の米の「稲穂」を、外側に「雪の結晶」を形どっている。
厳しい北国の自然にも負けずに、一生懸命開拓した昔の人たちの努力をほめたたえかんしゃし、あわせて東から昇るる太陽のように、みんなのことを考え、明るく強い心(意志)をもった立派な(人間性豊かな)人に育ってほしいという願いがこめられている。

|

