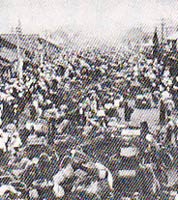 |
| 円山朝市 |
人々は、「明るくなってもねているのはもったいない。」と言って、夜が明ける前の暗いうちから起きて仕事を始めました。起きるとすぐに、男の人は馬の世話をし、田畑に出かけて野良仕事をします。女の人は、せんたくやすい事にとりかかります。朝市の開かれている時期は、夜中の1時2時に起きたものでした。
ひと仕事終えてから朝食です。主食は、わずかな米に、だいず・とうきび・あわなどをまぜたもので、おかずは、できるだけ買わないで、自分の家でとれた大根やたいなのつけものとみそしるでした。みそしるのみも、畑でとれたにらや、なっ葉でしたし、みそも自家製でした。大根の葉もすてないで、ゆでてからかわかして、とっておきました。冬のみそしるに入れるためです。こうして、自分たちの手でまかなったのです。
6時ごろに朝食が終わると、さっそく、田や畑に出かけます。力仕事をしておなかがへるので、9時か10時ごろには、「小昼」といっておやつを食べます。
昼食は、家の近くで働いていた時は、家にもどって食べますし、遠くで働いていた時は、ごはんの入っているおはちを、そのまま持って行って畑で食べました。おかずは、すしにしんやつけものです。
食べた後は、1時間ほどごろねをして体を休めます。
それからは、「手もとの見えるうちは働く。」と言って、暗くなるまでいっしょうけんめい働きました。暗くなって、やっと田畑の仕事をおしまいにします。その後で、馬のえさのために、田畑のふちの草をかるのです。そして、かりとった草を馬の背に積んで、暗くなった道をとぼとぼともどるのです。
それから夕食です。
夕食が終わった後、もうひとしごとするのです。暗くなってもできることは、昼間はやらずに残しておくのです。そして、うす暗いランプの明かりや月の光のもとで、明日の朝市に出す作物のより分けや箱づめをします。
冬になると、男は、なわないや、むしろ作り、わらじ作りをしました。女は、はり仕事に粉ひき、まめよりなどをするのです。
こうして、昼間のつかれをがまんしながら、夜おそくまでしごとをしてからとこにつくのでした。
そのころの家は、まだそまつなものでしたから、寒さのきびしい日には、朝起きてみると、息がこおって、ふとんの上がまっ白になっていたということです。それをかわかすのが、女の人や子どもたちの仕事でもありました。
自然に生えている桑を利用してかいこをかったりもしました。幼虫の葉を食べる音が、まるで雨が葉にあたった時の音のようにザワザワと聞こえたというほどでしたから、とてもさかんだったようです。しかし、苦労が多いわりにしゅう入が少ないので、明治の終わりごろには、だんだんとやめる家が多くなりました。
このころになりますと、堀立小屋から土台つきの家にだんだんと建て変わってきます。建てられた家の中には、遠くはなれたふるさとをなつかしんで、本州の時と同じようなゆかの高い風通しのよいえん側などをつけた家もあり、北海道の寒さに合うような家になるのは、ずっと後のことです。
だんぼうは、まだ、いろりが使われていました。ストーブが広く使われるようになったのは、昭和の初めごろからだそうです。
入植の初めから大正の中ごろまで、このあたりの家庭では主に「カンテラ」を明かりとして使っていました。三本に分かれている木のえだなどを台にし、その上にかんを置き、かんの中に油を入れ、しんをその中にひたし、しんに火をつけて明かりにしたのです。わずか4合の油で3か月ぐらい使ったそうです。また、カンテラは1家にひとつぐらいしかなく茶の間に置いてあったそうですから、ずい分暗かっただろうと思われます。
そして、だんだんとランプも使われるようになってきました。ランプは、しんの太さによって明るさが決まります。しんの太さは、2分、3分、5分とあり、5分しんだととても明るいのですが、油のなくなる量も早いので、たいていの家庭では2分しんのランプを使っていました。ほやというランプのガラスの部分は、すぐにすすだらけになり、毎日そうじをしなければなりません。ほやそうじは、手の小さい子どもの仕事と決まっていました。
 |
| ランプから電気へ |
1合は、1.8デシリットル。 4合で、7.2デシリットル。
1分は、3ミリメートル。 2分だと、六ミリ。 3分だと、9ミリ。
5分だと、1センチ5ミリメートル
電気の明かりがついたのは、ずっと後の昭和17年(1942年)でした。電気の明かりにするために、部落の人みんなが出て、電柱のあなをほったり電柱を運んだり、たいへんな苦労をしたそうです。苦労をした末に、ようやく電気の明かりがついた時は、明るくて明るくてとても感げきしたということです。
飲み水は、ほとんどの家庭で川から引いた用水の水を使いました。朝早くくんで、台所の大きなかめにためておいて使いました。ですから、水はとてもだいじに使いました。また、ほり井戸のある家もあったそうです。
おふろは、みきが太くてまん中がくさった、かつらなどの木から作りました。大木をてきとうな長さに切り、中をくりぬき、底にてっぱんをはりました。夏の間は、川の近くに置いて、わかしました。また、「ごえもんぶろ」という鉄なべの大きくしたものをふろにして入っていた家もありました。夏は、毎日。冬は、5日〜1週間に1ぺんぐらいのわり合いで入り、あせを流しました。
このころの便所は、どうなっていたのでしょうか。
便所は、たいてい家の中にひとつ、外の納屋にもうひとつ、というふうに2つぐらい用意されていました。おけを土の中にうめこみ、丸太を半分に切ってわたし、そこに足をおいて用をたしました。ですから、とても不安定でこまったということです。入口は戸ではなく、むしろを1まい下げておくだけだそうです。紙は使わず、ふきの葉を取って来てためておき、それを使ったりしました。便所のおけが半分以上になると、それを肥料として使いました。
ほとんどの家では、犬やねこを数ひきずつかっていました。犬は、はなしがいです。ねこは、大切な米などを食べるねずみ退治のためなどに、かっていました。
にわとりも、はなしがいで、庭の周りにかっていました。鳥小屋の中に入れておいても、いたちが、にわとりをおそうので、かえって、はなしがいにしておいたほうがよかったのです。庭先に木を横にわたしてにわとりがとまれるようにしていました。見えない草かげなどでたまごを生み、ひなに、かえした親鳥が何わもの、ひなをつれて出てくるということもよくあったそうです。
このころの服そうは、もめんのぬのを、さしこに仕上げたものや、島田の着物にうんさいのもんぺ、そして、さなだひもといういでたちが多かったようです。
冬は、ネルのシャツにわた入れのそでなし、それに、ももひきをはいたり、乗馬ズボンにゲートルをまいたりしました。
外出する時は、夏は、わらぞうりやとうきびぞうり、冬は、わらぞうりにぬのをはりつけた、ぼっこぐつやつまご、深ぐつをはき、女の人は、おこそずきんをかぶり、角まきをはおりました。
和服からしだいに洋服へと変わっていったのは、昭和になってからです。
| さしこ(刺し子) |
布を重ね合わせて、それを1針ずつ細かく縫ったもの。大変丈夫で、消防服や柔道の稽古着などに使われる。 |
| うんさい(雲斎服) |
布地を荒く斜めに織った布。足袋(たび)の底などに使われる。 |
| ネル(フランネルの略) |
毛糸で荒く織った柔らかい織物。 |
| ゲートル |
布または革製で、足首からふくらはぎまでまき上げておおうもの。 |
| おこそずきん |
目の部分だけ出し、頭や顔などを包むもの。主に婦人が防寒用につける。 |
| 角まき |
毛糸の肩掛け。大型で四角。婦人が主につかった。 |
札幌市立福井野小学校郷土誌「福井野に生きる」3訂版より転載

|

